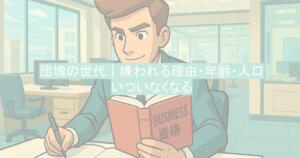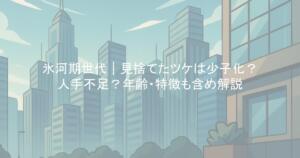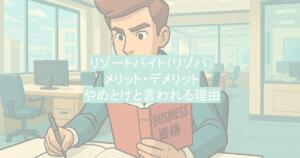『終身雇用はもう終わった』とよく言われますが、実際には約半数の企業が制度を継続しているのをご存知でしょうか。2019年のトヨタ社長発言以降、終身雇用崩壊の議論が活発化していますが、正確に言えば、『完全消滅』ではなく『形骸化』が実態に近いのです。
本記事では、日本独特の雇用制度の現状と海外との違い、さらに個人が取るべき具体的なキャリア戦略まで、データと事例を交えて詳しく解説します。
終身雇用崩壊論の真相
「終身雇用は完全に消滅した」と言われることもありますが、実際には多くの企業が制度を継続しているのが現状です。
こちらでは、終身雇用崩壊論が語られる背景と、現在進行中の制度変化について、最新データと具体的な事例を交えて詳しく解説します。
終身雇用が崩壊する3つの理由
なぜ終身雇用は崩壊すると言われているのでしょうか。
- 経済成長の鈍化
- 労働者の価値観の多様化
- 成果主義の加速的な導入
主にこの3つが大きな要因です。
バブル崩壊後、右肩上がりの経済成長が終わり、働き方改革によって多様なキャリア志向が生まれ、グローバル競争の中で実力評価が重視されるようになりました。これらの要素が重なり、終身雇用は議論の域を超えて現実として崩壊が進んでいるのです。
現在の終身雇用制度の変化
終身雇用制度は完全に消滅したのでしょうか。結論として、答えは「いいえ」です。現在は成果主義と併用する企業が増えており、富士通が2025年度からジョブ型雇用を本格導入するなど、制度の見直しが進んでいます。
また、リスキリングへの投資を拡大する企業は全体の半数を超えており、ポートフォリオ型キャリアの考え方が新たな常識として浸透しつつあります。 終身雇用崩壊論が語られる中で、制度に依存せず、自分に合った働き方を主体的に選ぶことがますます重要になっているのです。
世界から見た日本の終身雇用制度
日本の終身雇用制度は、世界的に見ると非常に特殊な雇用慣行です。
米国では「employment-at-will(随意雇用)」の原則により解雇が比較的自由で、成果に応じた報酬体系が主流となっています。一方、欧州では解雇規制は日本と同じく厳しいものの、ドイツのデュアルシステムのように、転職を前提とした技能資格制度が整備されており、労働市場の流動性が保たれています。
こうした国際比較を踏まえると、終身雇用崩壊の議論が進む中で、日本の雇用制度がいかに独特か改めてわかります。
海外の雇用制度との違い
米国では平均転職回数が11.7回にのぼり、特にIT業界では2~3年ごとに転職してスキルアップを図るのが一般的です。
外資系企業や欧米企業の多くはジョブ型の人事制度を採用しており、個々のスキルが外部の労働市場で適正に評価され、賃金は成果に応じて決まります。一方、日本では1回の転職で平均して約8.6社に応募するとされ、平均転職回数はおよそ2回にとどまっています。
これは米国の水準と比べると圧倒的に少なく、日本の雇用市場が閉鎖的であることを物語っています。終身雇用崩壊論が活発化する中、勤続年数を重視する従来の考え方から、成果を評価軸とする仕組みへの転換は避けられない状況です。
終身雇用制度の利点とは?
終身雇用制度には、従業員と企業の双方にとって明確なメリットがあります。
こちらでは、制度が生み出す具体的な利点を解説します。
従業員が得られる利点は?
終身雇用制度は従業員にとって「安定の象徴」として機能してきました。定年までの収入保証により経済的安心感が得られ、住宅ローン審査も通りやすくなるというメリットがあります。企業への帰属意識が高まり、愛社精神がモチベーション維持に直結するのも大きな特徴です。
ところが、終身雇用崩壊の議論が活発化している現在、これらのメリットは過去のものになりつつあります。
企業が得られる利点は?
企業が終身雇用制度を採用する理由は明確です。離職率低下による採用コスト削減が最大のメリットで、長期育成により企業特殊的技能が蓄積し、技術流出リスクを低減できます。
さらに、従業員の長期在籍により、カイゼン活動やQCサークルなど現場主導の改善文化が根付きやすくなります。組織文化の継承と企業独自のノウハウ蓄積により、競合他社との差別化を図ることが可能です。
終身雇用制度の欠点とは?
終身雇用制度には多くのメリットがある一方で、現代のビジネス環境では深刻なデメリットも指摘されています。
こちらでは、制度が抱える具体的な欠点を解説していきます。
従業員が直面する欠点は?
終身雇用制度は従業員にとって「安定の代償」が重すぎます。最大の課題はキャリア選択の制約で、従業員が企業特殊技能のみに依存することで、専門スキルの市場価値が見えづらくなることです。
雇用保証が逆に努力意欲を減退させ、リスキリング支援の遅れがAI時代の職務適応を困難にしています。終身雇用崩壊の議論が活発化する現在、自律的なキャリア構築が急務となっています。
企業が抱える欠点は?
企業が終身雇用制度で直面する最大の危機は人件費高騰です。年功序列によって中高年比率が上昇し、若手への投資余力が縮小しています。
特に深刻なのがDX人材不足で、解雇困難により経営の柔軟性が大きく損なわれています。終身雇用崩壊のリスクが高まる中、人事担当者は制度の抜本的見直しを迫られているのが現状です。
まとめ
終身雇用崩壊論の本質は「制度の柔軟化」であり、完全消滅ではありません。経済低成長と価値観変化により制度は多様化局面に入っており、社内外で価値を更新し続ける人材が重要な存在となる時代が到来しています。
具体的な行動指針として、新卒の方は会社内OJTと外部スキル取得を両立することが重要です。転職検討者はジョブ型求人と副業で専門性を検証し、人事担当者は「ハイブリッド制度」の設計が急務となっています。ジョブ型とメンバーシップ型を併用した柔軟な人事制度の構築が求められます。
変化する雇用環境において、終身雇用崩壊を前提とした自律的なキャリア構築が現代の重要な課題となります。最近では副業への意識が高まり、tims-fuku.workで紹介されている令和の虎の社長の経営している企業で動画編集を学んだり、自ら起業し、令和の虎にて資金の調達を試みる志願者も多くいると思います。制度に依存せず、自分自身の価値を高め続けることが何より大切だと感じています。